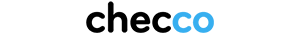汗かぶれ(顔)の治し方を徹底解説します

夏の暑い時期や運動後など、顔に汗をかいた後に赤みやかゆみ、ヒリヒリ感などの症状が出ることはありませんか。その症状は「汗かぶれ」かもしれません。汗かぶれは、正しいケアと予防策を知ることで、早期改善と再発防止が可能です。この記事では、原因から治療法、セルフケア、予防法までを徹底解説します。
汗かぶれとは?
汗かぶれの定義と症状
汗かぶれ(汗あれ)は、汗に含まれる塩分やアンモニアなどの成分が皮膚に刺激を与え、炎症やかゆみ、赤み、ヒリヒリ感を引き起こす皮膚トラブルです。特に顔は皮膚が薄くデリケートなため、汗かぶれが起こりやすい部位です。
あせもとの違い
汗かぶれは肌の表面に炎症が広がるのが特徴で、あせもは汗腺の詰まりによって内部に発疹ができる点が異なります。両者は混同されやすいですが、ケア方法が異なるため正しい見分けが重要です。
汗かぶれの主な原因
①汗をかいた後、そのまま放置することで塩分やアンモニアが皮膚に浸透し炎症を起こす。
②皮膚のバリア機能(皮脂膜)が低下していると、汗の刺激を受けやすくなる。
③紫外線やエアコンによる乾燥、ゴシゴシ洗いによる角質層の損傷もリスク要因。
顔の汗かぶれの治し方
1. すぐに汗を拭き取る
汗をかいたらすぐに、清潔なハンカチやタオル、ティッシュなどでやさしく押さえるように拭き取りましょう。肌をこすらず、押さえるようにするのがポイントです。
2. 洗顔・シャワーで清潔を保つ
帰宅後や運動後は、ぬるめのシャワーや洗顔で汗や汚れを洗い流します。ゴシゴシ洗いはNG。泡立てた洗顔料でやさしく洗いましょう。
3. 保湿ケアを徹底する
洗顔やシャワー後は、保湿剤や化粧水でしっかり保湿を行い、皮膚のバリア機能を高めましょう。べたつかず汗腺を塞がないローションタイプがおすすめです。
4. 市販薬の活用
赤みやかゆみが強い場合は、抗炎症成分配合のかゆみ止めクリームや、ステロイド軟膏を用いてみるのも効果的です。用法・用量を守って使用し、症状が改善しない場合は皮膚科を受診しましょう。
5. かゆみを我慢せず冷却
かゆみが強い場合は、濡れタオルや保冷剤で患部を冷やすと症状が和らぎます。爪でかきむしると症状が悪化するので、絶対に避けてください。
6. 皮膚科の受診
セルフケアで改善しない、症状が悪化する、広範囲に広がる場合は早めに皮膚科を受診してください。医師の診断のもと、症状に合った治療薬が処方されます。
汗かぶれの市販薬
【muHI(ムヒ)】アセムヒEX
容量:15g 価格:1,320円(税込)
汗をかくたびにかゆくなる、汗かぶれの治療薬です。
【小林製薬(コバヤシセイヤク)】キュアレア
容量:8g 価格:1,000円(税抜)
顔などのかゆみやかぶれに。
【田辺三菱製薬(タナベミツビシセイヤク)】指定第2類医薬品コートfMD軟膏
容量:10g 価格:1,485円(税込)
赤ちゃんの薄くて薬剤の浸透しやすい皮膚にも使える、軟膏タイプの外用剤です。
日常生活での注意点と予防法
汗をかいたらすぐ拭く・着替える
汗をかいたらこまめに拭き取り、必要に応じて着替えましょう。外出時は吸水性の良いタオルやウェットティッシュ、着替えを持参すると安心です。
通気性の良い服装を選ぶ
顔周りに触れる帽子やマスク、衣類は通気性・吸汗性のよい素材を選びましょう。締め付けや摩擦の少ないデザインが理想です。
エアコンや扇風機を活用
室温や湿度が高いと汗をかきやすくなります。エアコンや扇風機を上手に利用し、汗をかきにくい環境を作りましょう。
刺激の強い日用品は避ける
スキンケア用品や日焼け止めは、低刺激・無香料・アルコールフリーのものを選びましょう。異常を感じたらすぐに使用を中止してください。
食生活・生活習慣の見直し
辛い食べ物やアルコール、熱いお風呂は体温を上げてかゆみを悪化させるため控えましょう。十分な睡眠やバランスのよい食事で肌の健康を保つことも大切です。
汗かぶれのQ&A
Q. 汗かぶれは自然に治る?
軽度の場合はセルフケアで改善することもありますが、かゆみや赤みが強い場合、長引く場合は皮膚科での治療が必要です。放置すると悪化や色素沈着、痕が残ることもあるので早めに対処しましょう。
Q. ステロイド外用薬は顔にも使える?
顔は皮膚が薄くデリケートなため、使用する場合は顔用かつ弱めのステロイドを選び、短期間・少量を守りましょう。不安な場合は必ず医師や薬剤師に相談してください。
Q. 汗かぶれを繰り返さないためには?
汗をかいたらすぐ拭き取る、保湿を徹底する、通気性のよい服装を心がけるなど、日常生活での予防策を継続することが再発防止につながります。
汗かぶれに気づいたら早めに対処しよう
汗かぶれは、顔に起こりやすい身近な皮膚トラブルですが、正しい知識とケアで早期改善・再発防止が可能です。こまめな汗の拭き取り、優しい洗顔と保湿、適切な市販薬の活用、そして必要に応じた皮膚科受診がポイントです。自己判断が難しい場合も同様に、早めに医師に相談しましょう。